誰もがいつでもどこでもあらゆる情報を手軽に入手できる時代。
膨大な量の情報が常に脳へと届けられ、脳はその処理に来る日も来る日も追われているのではないでしょうか。もしかしたら『もう限界!』というサインを発しているのかも。
この記事では、脳が情報量やその処理能力に関してオーバーフローを起こし、それに伴い脳に関する機能が低下した状態である情報過多シンドロームについて述べていきます。
情報過多シンドロームとは
携帯電話・スマホは急速に進化し、膨大な量の情報をネット上からやり取りすることができますが、それを処理する脳の機能は飛躍的に向上しているわけではありません。
また、脳のキャパシティは本来決まっていて、一度にインプットできる情報量とそれを処理する能力には限度があります。
つまり、遅かれ早かれ脳がオーバーフローを起こしてしまうことは予測ができたことになります。
近年、記憶力や判断力、理解力等が低下してしまう社会人の方が増えてきているようで、こうした脳の機能不全の状態は情報過多シンドロームと呼ばれています。
以下の関連情報によると、この症状の名付け親は東京脳神経センターの天野惠市先生として紹介されています。
◆―関連情報―◆
情報社会の新たなSOS。情報過多シンドロームとは/サワイ健康推進課
自分の中で情報フィルターを機能させる
情報過多シンドロームを防止するためには、一度にインプットする情報量を抑制する必要があります。
そのためには、自分の中で情報フィルターを意識的に機能させ、主にスマホからインプットされる情報を制限していく必要があるということです。
といっても、ネットサーフィンをしていると、ついつい下へ横へと際限なくスクロールしてしまいますよね。ですが、そこを意識的にブレーキをかけていくということです。
急には難しいかもしれませんが、自分の脳への思いやりと思えばきっとできるはずです。あなたはもう情報過多シンドロームの知識を得ているのですから。
とにかく、『あれ、この情報っていまの自分に本当に必要かな?』と自問自答することからはじめてみてはいかがでしょう。

そのような意識を持てるようになったら、次は「不要」と判断された情報は断捨離のようにどんどん捨てていったり、そもそも取り入れないということが大切になりますね。
冷静に個々の情報と向き合えるようになったとき、自分の身の回りは思った以上に必要のない情報で溢れていることに気づくはずです。
それと似たような状況は郵便ポストの中でも日々発生しています。蓋をあけると結構いろいろと届いていますが、いまの自分に本当に必要な情報は1つか2つ、またはゼロの日もありますよね。
SNSとどう付き合うか
あなたが頻繁にアクセスしている情報源の1つにSNSがあると思います。これとの付き合い方も一度、よく考えておく必要があります。
なぜなら、SNSは情報源であるとともにストレスの発生源にもなっているからです。ストレスが生じる主な原因は「人と比べてしまう」という点です。
SNSは人のプライベートを覗き見しているようなところがあります。他人のプライベートって、週刊誌のゴシップ記事のようについつい気になっちゃいますよね。
ですが、そこで公開されている情報を見て、これまたついつい自分と比較してしまうところがあります。
SNSで公開されているキラキラした情報(強みの部分)を相手に、なかなか自分が勝利することは難しく、結果として自信を低下させたり、場合によっては妬みや嫉妬の気持ちが生じてくることもあるでしょう。
つまり、SNSは他人のプライベートを覗き見しているものととらえれば、「別に見る必要のないもの」「知る必要のないもの」となり、脳への負担軽減のためにも少し距離を置くことが望ましいということになりますね。
◆ カテゴリー:ストレス

プライベート情報は本来は親密な人間関係を促すもの
本来、プライベートな情報は相手との仲を深めるという役割を果たしています。あなたも経験があると思いますが、表面的、社交辞令的なやりとりだけでは、なかなか親密になることは難しいですよね。
そこに出身地や趣味等といったプライベートな話題が入ることで、その人との距離を徐々に縮めていくことができました。

ただ、それは本人から相手に対して情報が開示された場合です。あなたのことを信頼して、あなたと仲良くなりたりからこのことを教えてあげる、という流れで開示される形が理想的です。
そうすると、自己開示の返報性の原理が働き、あなたもその相手に対してプライベートな情報をスムーズに開示でき、その相互のやり取りを通じて親密になっていけるというわけです。
このように、プライベートな情報は社会的なつながりをより強固にする上でとても大切であるといえます。
ですが、不特定多数のユーザーに対して一方的に開示されるSNSからの情報は、(見かけ上の)表面的なつながりを作るだけのものかもしれません。
そのような情報は、いまのあなたにとって本当に必要なものでしょうか??
◆ カテゴリー:コミュニケーション

脳の情報過多を防ぐのはけじめのある使い方!?
いつでもどこでも手軽に多様な情報を入手できるスマホは別に悪い代物ではありません。こと情報過多に関しては、それを使う私たちに問題がある可能性があります。
いま、ながらスマホが社会問題化しています。歩きながらスマホ、自転車・自動車を運転しながらスマホなど、要はけじめのない使い方をしてしまっているということです。
スマホを使う時とそうでない時を意識するだけでも、脳における情報過多の状況はかなり和らいでくるのではないでしょうか。
極端な話、ほぼ一日中スマホを使っていることもあるかもしれませんし、そんな時は脳がオーバーフローしてしまうはずです。
私たちは足腰など、身体が疲れたと感じたら適度に休憩を取りますが、その考え方を脳にも積極的に適用してあげる必要がありそうです。
『スマホを使わない日を作るのは無理』という場合は、けじめのある使い方から意識してみてはどうでしょうか。
まとめ
物事には必ず光と影の両面があります。
高度情報化社会の恩恵はあらゆる情報にいつでもどこでも手軽にアクセスできる環境の構築であり、その負の側面は脳への負担増大とSNSという新たなストレス源の出現です。
スマホもSNSも、一昔前には存在しなかった画期的な代物です。情報機器は急速に進化していますが、その処理を担う脳のキャパシティには限度があります。
あなたの中で情報フィルターを機能させ、情報の必要不必要を意識するようにしてみてください。また、主に視覚から情報をインプットする時間にもけじめが見られるといいですね。
あなたが子どもの頃、きっと家ではテレビを見る時間にけじめがつけられていたと思います!
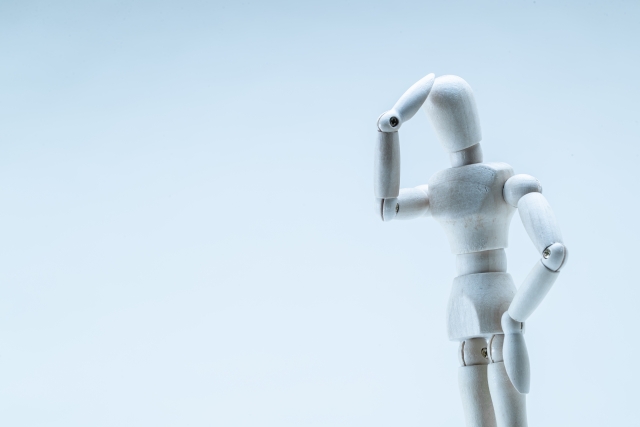

コメント